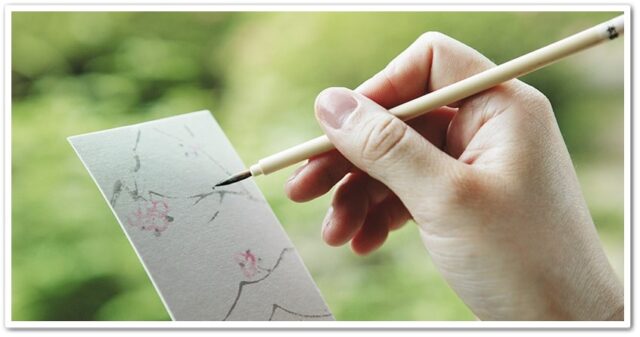
世界最短の定型詩のうちのひとつ
五・七・五で完結する日本独自の短詩
日本伝統文化のひとつ
『俳句』
「俳諧の句」という言葉の略
17語に思いを寄せて詠み手の心情や
情景を詠んでくれる詩です♪
鎌倉時代~江戸時代に庶民に大流行し
みんなが趣味として楽しんでいました
和歌の上の句(五・七・五)
和歌の下の句(七・七)
これを互いに作り合い1つの詩にする
「俳諧連歌」というものがあります!
この冒頭にくる初句(五・七・五)
これが俳句になったと言われています。
俳句の魅力とは!
五・七・五の短い韻文に季語を入れる
この最低限のルールを守れば誰でも
どこでも自由に作れる気軽さが魅力♪

また
季節の移り変わりの情緒や日常が凝縮
された世界で一番短い文学なんです。
んっ!季語って何?
必ず入れる季節感を表す言葉。
春夏秋冬の季節に分けた四季
大陰暦で二十四の時節に分けたもの
時候、天文、地理、生活、行事、動物、植物
これらを表す季語を一つ入れる事です
ということで今回は俳句の季語について
簡単に紹介したいと思います。
面白い季語も季節ごとに紹介します♬
あなたも特待生になれるかも…(笑)
(*^_^*)<古池や~蛙飛びこむ水の音~♪
俳句の季語
特定の時季を表すための「季語」です。
簡単に言えば季節がイメージできるもの
まずは有名な俳句を紹介しますね!
小林一茶・正岡子規・与謝蕪村などなど
その中から!
俳聖と呼ばれた俳人「松尾芭蕉」
春夏秋冬ごとの俳句をご覧ください♬

●
「古池や 蛙飛びこむ 水の音」
季語は“蛙” 季節は“春”

「荒海や 佐渡によこたふ 天河」
季語は“天河” 季節は“夏”

「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」
季語は“名月” 季節は“秋”

「水仙や 白き障子の とも移り」
季語は“水仙”“障子” 季節は“冬”
どうですかこれらが季語ですよ♪
伝統俳句の季語は一つがルールですが
無季自由律俳句は絶対ではなくて自由
季語を入れない句や季語を2つ入れたり
これは明治末におこった新傾向俳句が
急進して大正半ばで自由律として確立。
珍しい季語
基礎的な季語は長い歴史のなかで
昔からの名句の蓄積によって定着
「歳時記」という書物に1年おりおりの
自然・風物・四季などの言語を分類して
解説や例句を示した書があります。
もちろん「歳時記」に載ってなくてもOK
ただ季節と関係ないものはNGなんです

●
それではこれって季語!?
珍しい季語をいくつか紹介します♪
《春の季語》
「ボートレース」・「アスパラガス」
「子猫」・「猫の恋」・「海苔」・「菜の花」
「エイプリルフール」・「バレンタイン」
「ゴールデンウィーク」・「ピアノ」

●
《夏の季語》
「甘酒」・「サングラス」・「ブランコ」
「アイスコーヒー」・「稲川淳二」・「汗」
「プール」・「アメンボ」・「プール」
「幽霊」・「サザンオールスターズ」

●
《秋の季語》
「小豆」・「夜食」・「スイカ」・「運動会」
「朝顔」・「花火」・「相撲」・「お盆」
「八月」・「墓参り」

●
《冬の季語》
「浅漬」・「おでん」・「ニンジン」・「鮪」
「有馬記念」・「ラクビー」・「ユーミン」
「山下達郎」・「寅さん」・「紅葉」

●
季語の季節は旧暦になっているので
新暦の現代では季節にズレがあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

芸能人の名前が季語!
有名な行事も季語に!
びっくりしました~♪
まとめ
いかがでしたか!?俳句の季語
現代では多くの季語が追加されて
約5000もの季語があるそうです
ただ季語には正式に認定する機関や
書籍があるわけではありませんので
あまり気にしなくても大丈夫です♪
================
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
俳句の季語






